電動モビリティで地域の観光振興と二次交通の課題解決に挑む
株式会社マスヒロ
代表取締役 増子 博之

本事業では、地域内外の中小企業・スタートアップや大企業、大学等が連携して、地域の課題解決を図るためのプロジェクトや、多様な主体が交流できる会員組織(コミュニティ)の立ち上げなど、イノベーション創出に向けた取組を進めています。このインタビュー連載では、多摩地域のイノベーションをリードする注目企業をご紹介することで、皆様に多摩地域の魅力を発信していきます。
電動キックボードで、日常に“冒険”と“感動”を。50歳を機に28年勤めた消費財メーカーを退職し、株式会社マスヒロを立ち上げた増子博之氏。電動モビリティの規制緩和やインバウンド需要の高まりに着目し、引率者付き電動キックボードのガイドツアーを軸に、新たなサービスを展開しています。さらに、電動キックボードを活用して地域の活性化や“二次交通”の課題解決にも挑戦する増子氏に、事業内容について話を伺いました。
日本の四隅を巡って見えてきたこと
- まずは起業に至った経緯を教えてください。
増子:外資系の消費財メーカーに営業職として入社し、28年間勤めました。扱っていたのはタバコ。市場の成長期、成熟期、そして衰退期まで、浮き沈みのすべてを経験しました。ある意味で、やり切ったという感覚があったのです。50歳を迎え、自分のスキルを生かして何か新しいことに挑戦できるのではないか。そう思い立って退職しました。でも、正直なところ、自分に何ができるのかは分かりませんでした。そこで、まずは日本の“四隅”を見てみようと決めたんです。日本の東西南北の果てを巡る旅に出ました。最初は途方もない旅に思えましたが、実際に行ってみると、思ったほど時間がかかるわけでもない。「遠く見えても、進めばちゃんとたどり着ける」。そう実感しました。何かを始める前は、つい物事を大きく構えてしまいがちだけれど、実際に動き出してみれば現実的な距離で目指せるものなのだと。この体感は、ビジネスを作っていくうえでの、大きな学びになったと思っています。もともと「起業家」といった華やかなイメージとは縁遠い自分でしたが、あの旅を経て、「自分にもできるかもしれない」と、初めて心の底から思えました。
- なぜ電動モビリティの事業をやろうと思ったのですか?
増子:2021年に起業しようと決意したのですが、電動モビリティに関する規制が2年後の2023年に緩和されることは、当時すでに見えていました。加えて、国策としてインバウンド需要が今後ますます高まっていくことも明らかでした。そんな折、渋谷で外国人観光客がストリートカートを運転して楽しんでいる光景を目にしたのです。そのとき、「これの電動キックボード版があったら、もっと多くの人が気軽に楽しめるのでは」と直感的にひらめきました。ストリートカートは運転免許が必要ですが、電動キックボードは近く免許不要になる見通しがある。この「規制緩和」と「インバウンド」という二つの追い風を掛け合わせれば、新しいビジネスが生まれる。そう確信したんです。

電動キックボードで巡る体験型ガイドツアー
- 知的財産権の一つである実用新案権も取得された、電動モビリティを活用したガイドツアー『楽旅(ラクタビ)』について、ご紹介ください。
増子:『楽旅(ラクタビ)』は、観光地や自然の中を、ガイドの引率のもと電動キックボードなどのモビリティで巡る体験型ガイドツアーです。ツアーの主な特徴は以下の3点です。①ガイドによる引率付き。②インカム無線付きヘルメットを着用し、走行中でもガイドの案内を聞けるほか、参加者同士の意思疎通も可能。③引率者がツアー中の走行シーンを動画撮影し、編集データとして参加者に提供。
これらの要素を一つのパッケージとして構成し、商標登録および実用新案権を取得したのが『楽旅』です。もともと、インカム無線付きヘルメットはガイドの案内を一方的に聞いてもらうためのものとして導入しましたが、モニターツアーを重ねる中で、「少し離れてしまったときや、トイレに行きたいときなどにもすぐ伝えられて安心だった」という参加者の声が多く寄せられました。この機能が“安心感”という大きな付加価値につながっていることに気づかされました。また、走行シーンの動画は旅の思い出になるだけでなく、万が一トラブルが発生した際にはドライブレコーダーのような役割も果たすため、安心・安全の面でも効果を発揮します。
多摩地域の“二次交通”を電動キックボードで解決
- 御社のYouTubeチャンネルで、多摩地域のスポットを電動キックボードで巡る動画を拝見しました。
増子:あれは、多摩観光推進協議会との連携による取り組みです。多摩地域はとても広く、電車でアクセスしても駅から観光スポットまで歩かなければならない場所が多い。そうした“二次交通”の課題が、観光のネックになっています。観光客にとっては、限られた時間の中でどれだけ多くのスポットを巡れるかが重要です。そこで、もっと手軽に・楽しく・安全に周遊できる手段として、電動キックボードを活用したコンテンツでタイムパフォーマンスを高めれば、多摩の魅力を短時間で効率よく体験してもらえるのではないかと考えました。一方で、都心ではいまオーバーツーリズムが課題となっています。多摩に観光客の流れを誘導できれば、都心の混雑緩和にもつながりますし、多摩地域の観光活性化にも貢献できます。そんな考えのもと、多摩観光推進協議会との実証実験としてツアーを展開しました。具体的には、立川から観光バスに乗り、現地では電動キックボードに乗り換えて御岳山、秋川渓谷、酒蔵などを巡る内容です。広域を効率よく巡るには、大きな移動はバスで、細かな周遊はキックボードで、というハイブリッドな移動手段が理にかなっています。

電動モビリティだからこそ得られる没入感
- 電動キックボードが“アクティビティ”としても楽しまれている印象を受けました。
増子:そうなんです。たとえばオートバイだとエンジン音が気になりますし、自転車だと自分でこがなければいけない。そのぶん、どうしても意識が散漫になるというか、周囲に集中しづらいところがあります。でも、ハイキングだと鳥のさえずりや川のせせらぎが聞こえてきて、自然を五感で体感できますよね。電動キックボードをはじめとした電動モビリティのいいところは、音が静かであること。乗っている最中も、そうした自然の音がそのまま耳に入ってきます。結果として、風景や空気に包まれるような“没入感”が得られる。この感覚が、多摩の豊かな自然の魅力と非常に相性がいいんです。しかも、疲れることなく短時間で移動できるので、「歩くのはちょっと……」という人でも、ハイキングのような気分を気軽に楽しめます。

不便な地域でこそ価値を発揮するビジネスモデル
- 電動モビリティは、都心でのシェアリングサービスというイメージが強かったのですが、自然との相性も良いのですね。
増子:そうですね。現在広く展開されている電動モビリティのシェアリングサービスは、基本的に都市型のモデルです。言ってしまえば、すでに便利な街を、さらに“過剰に便利”にしている。その方向性自体はビジネスとして理にかなっていますし、企業が収益を求める以上、どうしても採算の取れるエリアに集中してしまうのは自然なことです。一方で、国や自治体の視点に立つと、“不便な地域”にこそ支援や施策の意義がある。そこに暮らす人々や訪れる観光客にとって、交通の不便さをどう解消するかは大きな課題です。私は、電動モビリティの力で地方の観光振興や二次交通の課題解決を実現したいと考えています。その姿勢が評価され、多摩観光推進協議会をはじめ、さまざまな自治体との連携にもつながっているのだと感じています。だからこそ、そこでしか出来ない、これでしか出来ない発想で探求を続け、地域の魅力を高めながら、唯一無二の価値へ転換して行きたい。
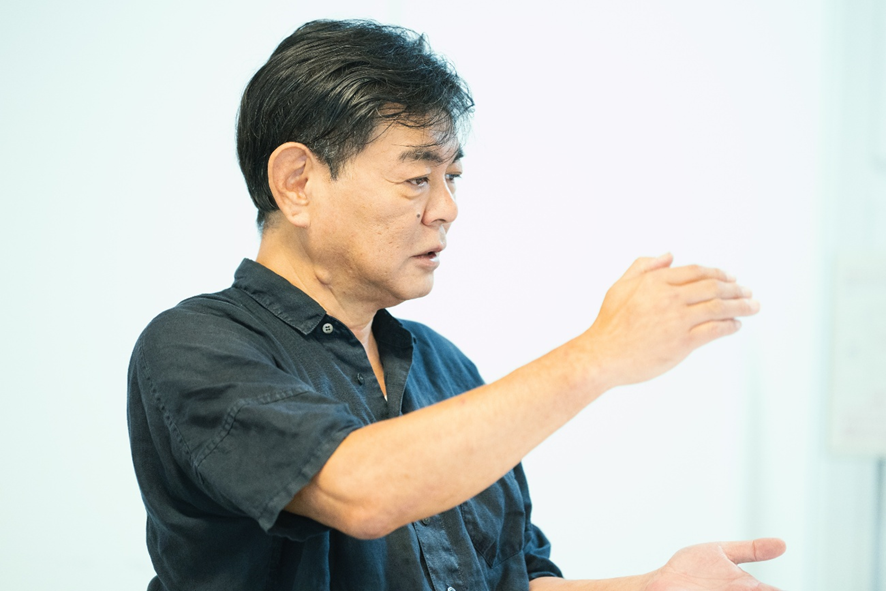
ガイド不足という課題を解決するために通訳案内士を活用
- 『楽旅』を全国に広げていくうえで、どのような課題がありますか?
増子:以前、大手旅行会社と京都でデモツアーを実施したことがあります。2泊3日で金閣寺などを巡る約8キロのコースでした。そこで見えた全国展開に向けた最大の課題は、「ガイド役の引率者が不足している」という点でした。この課題を解決するために、現在は通訳案内士を育成している企業との連携を進めています。街中で旗を持って観光客を案内している、あの専門ガイドの方々です。彼らはすでに語学力や観光地の知識、引率のスキルを持っているため、『楽旅』のガイド役として活躍していただければ、こちらの教育コストも抑えられますし、通訳案内士の方々にとっても新たな収入源になります。実際、この3年で『楽旅』のツアー引率ができる方も少しずつ増えてきました。一人で全部やろうとしなくても、協力し合えば大きなビジネスモデルは作れる。これこそがオープンイノベーションなんだと実感しています。
同じ志を持つ人たちを後押ししたい
- 最後に、今後の展望をお聞かせください。
増子:電動キックボードは、自動車と比べCO2排出量がはるかに少なく、環境面でも注目されています。ゼロカーボンのスマート・ツーリズム『楽旅』を全国に展開し、二次交通の課題解決や観光資源の活用につながるモデルとして育てていきたいと考えています。全国の地域で新たな産業や雇用創出に貢献し、事業をさらに拡大していきたいですね。最終的に目指しているのは、私のように一人でスタートした人間でも、「何かを始めたい」と思う人たちの背中を押せる存在になることです。全国には、若い人だけでなく、セカンドキャリアとして新たな挑戦を考えている方もたくさんいるはず。そうした人たちに、自分のビジネスモデルを伝えていきたいと思っています。フランチャイズという形式ではないですが、同じ志を持つ人が自分の手で事業を育てられるような仕組みを作りたい。そうやって、一人でも多くの“挑戦したい人”を後押しできたら、何よりうれしいですね。
会社情報
| 会社名 | 株式会社マスヒロ |
|---|---|
| 設立 | 2022年 |
| 本社所在地 | 立川市(支店・営業所) |
| ウェブサイト | https://masuhiro555.com/ |
| 事業内容 | 電動モビリティを活用したコンテンツ造成とソリューション支援 車体の販売・レンタル・リース・サブスク・保守/運用コンサルティング/映像制作(ドローン空撮含)・HP・LP・パンフレット制作 |


